2008年9 月
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 |
最近の記事
最近のトラックバック
- 二重星団 (天体観望のすすめ)
- 10/1 富士山新五合目観望の様子 (観望会報告と観望地)
- Nova Sct 2005 (ペット(犬:コメット)と家の近所や家族)
- こぎつね座 M27 (天体観望のすすめ)
- 惑星状星雲の楽しみ方 (天体観望のすすめ)
- へびつかい座の惑星状星雲 : NGC6309 : BOX Nebula (天体観望のすすめ)
- 惑星状星雲の楽しみ方 (天体観望のすすめ)
- 惑星状星雲の楽しみ方 (天体観望のすすめ)
- ペルセウス座の惑星状星雲 : M76 小あれい星雲 NGC650 (天体観望のすすめ)
- 惑星状星雲の楽しみ方 (天体観望のすすめ)
Powered by Typepad
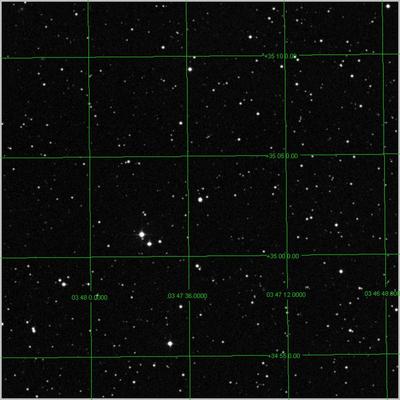
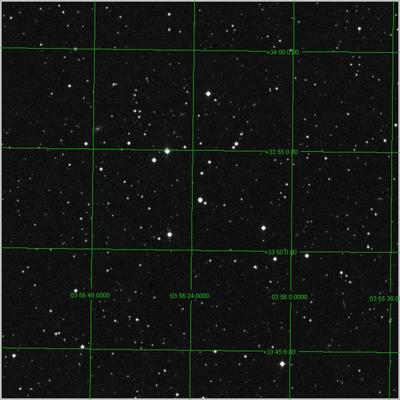


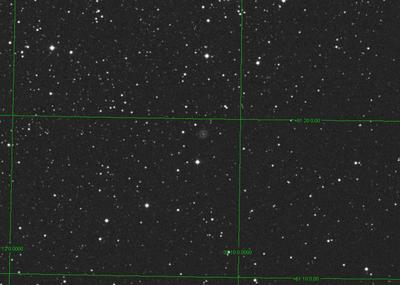
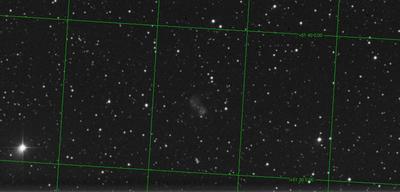

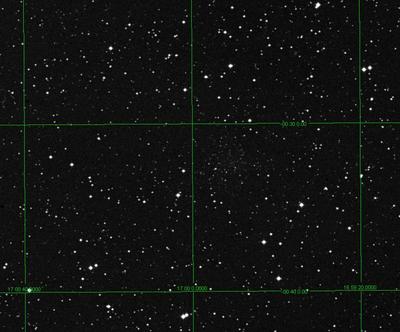
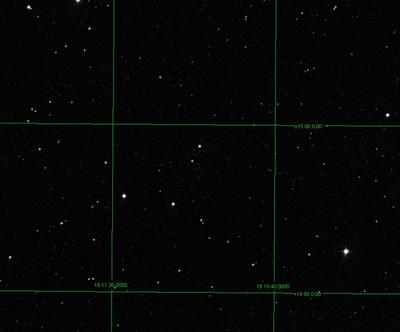
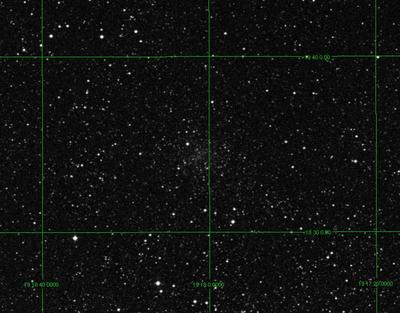
最近のコメント